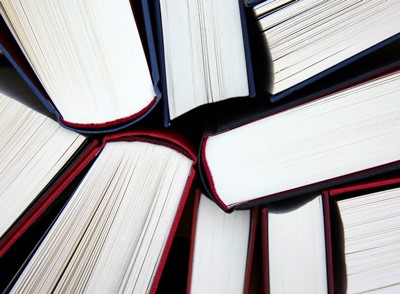今後のセラピスト業界を考える上で重要な7つの軸

 2015/11/01
2015/11/01 
中川逸斗(Nakagawa Hayato) 株式会社ケアレンツ 取締役
1984年大阪府生まれ。同志社大学卒業後、大手外資系コンサルティングファーム2社(IBMおよびDeloitte)で様々な業界のクライアントの経営戦略構築や業務改善、マーケティング、ITプロジェクト等に従事。その後、医療・介護系企業でミャンマー・台湾・ドバイなどの国際案件や国内の事業企画等に従事した後、現職。
Facebook:https://www.facebook.com/hayato.nakagawa.37
Facebook:https://www.facebook.com/hayato.nakagawa.37
PTOT関連の各種セミナーに参加させて頂くと、地域貢献・職域拡大・業界成長・維持などの観点から様々な議論が活発になされています。
特に、医療保険下、介護保険下以外の領域で、どのようにセラピストが活躍できるのか、そしてその土壌をどう作っていくのかということが議論なされていると感じます。
ただし、「予防の領域」「地域包括ケア」といったフワッとした結論になっていると第三者から見て感じます。
業界の新しい方向性を、より具体的に落とし込んでいくには、複数の軸の組み合わせで考えるのも一案だと思います。
その7つの軸とは、
①地域軸:都道府県・市区町村、海外など
②対象軸:高齢者・小児・障がい者など
③役割軸:教育する立場か、プレイヤーか
④時間軸:予防なのか、終末期か
⑤フェーズ軸:医療なのか、介護なのか、地域なのかなど
⑥手段軸1:徒手療法なのか、運動療法なのか
⑦手段軸2:リアルなのかWebなのかなど
上記の①~⑦の軸を組み合わせた上で
⑧ニーズ軸:利用者さん(当然、軸①や②で細分化された利用者さん)が何を求めているのかと照らし合わせます。
①~⑦の組み合わせでいうと、例えばこんな8つのモデル事例が考えられます。
【例1】
①地域軸(海外) × ②役割軸(教育者) です。
現在、私が台湾で活動している内容も、この領域です。
介護領域においては、日本は先進国なのでタイムマシン事業をできるかもしれません。
【例2】
①時間軸(終末期) × ②対象軸(高齢者) で、End of lifeにセラピストが関わるという発想も可能です。
【例3】
ビュートゾルフ(オランダの在宅ケア組織)は、①地域軸(小学校区) × ③役割軸(インフォマールケア)ですね。
【例4】
②対象軸(高齢者) × ③役割軸(コンシェルジュ)で、地域でのコンサルティング領域にも進出できるかもしれません。
【例5】
⑦手段軸2(Web)×③役割軸(マッチング)で高齢者の目標支援のための専門職とのマッチングも不可能ではありません
【例6】
④時間軸(予防)×③役割軸(アプリ開発)で、予防のためのアプリ開発も可能です。
【例7】
②対象軸(介護職)×③役割軸(教育者)で介護する人に専門職が教育するサービスも
どんどん生まれても良いかもしれません。
【例8】
③役割軸(教育者)×⑥手段軸(Web)
【例7】を発展させた形です。
セラピスト以外にセラピストのノウハウを伝授するモデルをスキーム化してもよいかもしれませんし、それをソフトウェアの力で実現することも可能ですね。
ぱっと思い付くだけでも、これだけあります。
もっと考えれば様々なアイデアが出てくると思います。
これらの軸は、もちろん網羅されているかは不明ですし、地域によってこの軸は大きく変化します。ただ、業界の方向性を議論し、収斂させていくためには、ある程度の軸をもって考えた方が考えやすい、分かりやすいという事もあります。
ディスカッションをする際に活用してみて下さい。
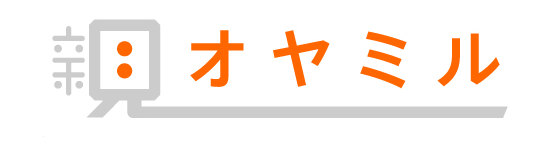
 ログイン
ログイン 会員登録
会員登録